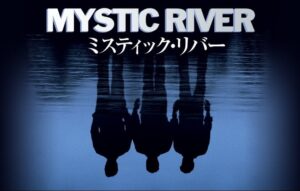コロナウィルスの影響で、何度も上映が延期されてきた映画『キングスマン:ファーストエージェント(The King's Man)』がやっと公開された。
一作目の『キングスマン(Kingsman: The Secret Service)』、二作目『キングスマン:ゴールデン・サークル(Kingsman: The Golden Circle)』では、資本主義によって生まれた大金持ちが、人体埋め込み式のICチップやウィルスワクチンを使って世界征服をたくらみ、キングスマンのメンバーたちがそれを防ぐ闘いが描かれていた。
躍動感あふれるアクションに加えて、キングスマンとしての成長、子弟を超えた友情の復活などが描かれていた。鑑賞後には爽快さと解放感を抱いたほどだった。
だが三作目を見た後では、面白かったはずの前二作がどこか小さく感じられてしまう。なぜそう思ったのだろう。その理由を考えながら今作を振り返ってみる。
歴史を踏まえた娯楽映画

シリーズ三作目の『キングスマン:ファースト・エージェント』は時代をさかのぼって、組織が誕生した背景を第一次世界炭という史実を踏まえて物語っている。戦争時に撮影された白黒の映像が繰り返し挿入され、そのどれもが過去に実際に起こった惨劇であると観客たちに伝えている。
だが物語の核となっている戦争が起きた背景の三国の王たちの対立は、日本人には馴染みのない出来事だ。それゆえヨーロッパ人と同じ感覚で理解することは難しいが、それであっても十分に楽しめる。ここがこの映画の強みだろう。
そしてこの作品の時代背景をもっと知りたいと思わせもする。そんな知識欲を刺激するのが『キングスマン:ファースト・エージェント』だ。
偉大な監督にならう姿勢

実際に起きた戦争の映像を作品に登場させるのは、ヨーロッパ出身の映画監督が用いてきた。ドイツ出身のエルンスト・ルビッチやフリッツ・ラング、イギリス出身のチャールズ・チャップリンがその代表として挙げられる。
偉大な先人たちは戦争をエンターテイメントの中に組み入れて、作品も観客に大いに支持された。その姿勢は攻撃に加担するでもなく、被害に寄り添うでもなく、中立であり続けた。戦争を後世に残していくには、事実を事実として映し出す記録でありながら、娯楽の要素も必要だと考えていたからだ。
世界の中心であろうとするイギリスが、そうであるために犯してきた陰謀と殺戮も隠すことなく描かれている。この姿勢は、自国の立場から善悪を語ることが常であるアメリカや日本とは大きく違っている。
監督のマシュー・ヴォーンはこの姿勢を受け継ぎ、『キングスマン:ファースト・エージェント』で見事に成しとげた。前二作に歴史的事実が加わることで厚みが増し、一回り大きく成長した作品になったと感じるのは、この要素があるからだろう。
もっと深く知りたいと思わせる

この成長は観客に知識欲求を沸かせることからも分かる。作品を観返すために再度映画館へ足を運ぶだけではない。おそらく多くの人が、映画の背景である第一次世界大戦が起こった経緯に興味を持ったのではないだろうか。
また過去の名作やヒット作を連想した人も多いかもしれない。『007』や『名探偵ポワロ』など母国イギリスのほかにも、『インディージョーンズ』や『ミッションインポッシブル』などのハリウッドのアクション映画も思い浮かぶ。監督では、先に述べたルビッチ、チャップリンのほか、オーソン・ウェルズ、デビッド・リーン、スティーブン・スピルバーグ、クリストファー・ノーランなど、独自の表現を大切にし、かつ作品を世界規模でヒットさせた巨匠たちだ。
このように『キングスマン:ファースト・エージェント』は、観て終わるだけでなく、そこから世界の歴史を知りたくなったり、旧作へと興味がわいたりなど、様々な視野を広げてくれる作品である。
感情と演出の妙
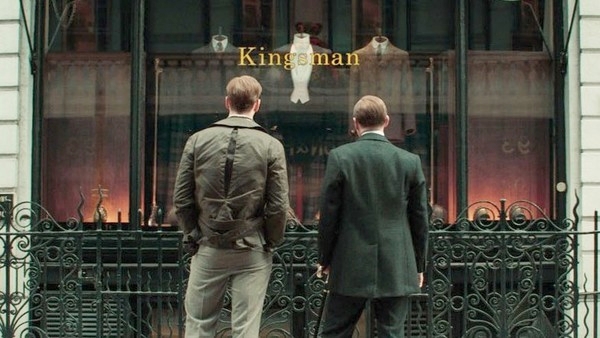
ここからは、物語の進行を追ってみよう。開始から三分の一ほどは王家の青年が身を隠して兵隊に志願し最前線へ行くまでだ。この過程では映像の色調、カメラワーク、音楽など、映画の表現手法すべてが抑えられている。およそ白黒といっても良いほど、映像からは鮮やかな色が排除されている。背後に流れる音楽は単調で小さい。カメラもほんの少しの横移動をする程度で、人物の感情を示す視点を外れることはない。これらの映画的な表現は、物語の中心人物である青年が自身の身分がゆえに抑えた気持ちを表している。監督は創作としての演出を極力なくし、観客を一兵士一市民として生きると決めた青年と同じ位置に立たせたかったのだろう。
一個人の思いから叙事詩へ

青年が仲間を救うために弾丸の飛び交う中を駆け回るあたりから、物語は映画としての特色を見せはじめる。カメラは人間の視点を離れ、躍動するように天地に大きく振れる視点を持つ。その激しさに応えるように、音楽は大々的なオーケストラへと変わる。身を隠した名もなき青年が、戦争を語る叙事詩の英雄へと飛躍したのにあわせているかのようだ。
ヨーロッパの貴族には、身分ある者には相応の責任があるとする「ノブレス・オブリージュ」精神があるという。だがそれゆえに失くした若い命と、その悲しみにどうすることもできない単に父というだけの男。社会的な身分と一個人にはさまれた辛さがキングスマンという組織をつくった。
四作目には日本も
映画は第一次大戦が終わりヒトラーが登場するシーンで幕を閉じた。これは間違いなく第四作を前提としたエンディングだ。次回作では独裁を強めたドイツやイタリアとともに、日本の軍人も登場するかもしれない。もっとも主要な取り扱いはないかもしれないが。
後味の良さに酔えるエンディング

マシュー・ヴォーン監督はこれまでの『キングスマン』でもクラッシック曲を効果的に用いてきた。それらは主に劇中で流れ、映像のコミカルさを増すユーモアがあった。そのセンスは今作ではラストのエンドロールで発揮されている。フル演奏される曲とクレジットが終わる時間がピタリと合い、最後まで観終わって心地よい印象を残してくれる。読後感の良い本があるように、観終わった後も長く楽しさが続く、そんな鑑賞の後味が良い映画である。ぜひエンドクレジットの最後までシートに座って観てほしい。
IMAXのようだが
ところでエンドロールにはIMAXという文字が見える。どうやらIMAXで撮影されたようだが、日本ではIMAX上映はされないようだ。というのも『マトリックス』や『呪術廻戦』がIMAX上映されるためた。『ファーストエージェント』がコロナウィルスで何度も上映が延期された影響は、こんなところにも出ている。残念で仕方がない。
才能豊かなスタッフ
『キングスマン』の原作者マーク・ミラーはまだ50歳ほどで、若いころから漫画やアニメ原作などを多く発表してきたという。そのいくつかは映画化もされている。2010年に公開された『キックアス』は彼が原作でマシュー・ヴォーンが監督と、今作の同じコンビだ。
ミラーの多才ぶりは、『X-メン』や『スパイダーマン』などを産みだした漫画やアニメの原作者スタン・リーに似ている。今後の活躍が期待できるクリエーターの一人と言える。
風刺の精神を受け継ぐ

イギリスはウィットを大切にし、何ごとにも社会風刺を取り入れて知性として笑うお国柄だ。映像での原点はチャップリンの放浪紳士だろう。その精神はテレビのコメディが受け継ぎ、モンティパイソンやMrビーンを産みだした。映画『キングスマン:ファーストエージェント』はこの後継者として、ウィットに富んだ台詞と仕草にあふれている。
また、国の成立を美化せずに、自らの醜い行為を認める正当な中立性を持ち合わせてもいる。この二つを創作物として、映画に盛り込んだ脚本家と監督の才能は素晴らしい。
次回作が待ち遠しい、そんな一作が『キングスマン』シリーズだ。