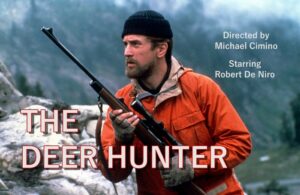木村拓哉氏が主演する映画がSMAP解散という日本全国を巻き込んだ事件の記憶が冷めないうちに公開された。ここに何か因縁のようなものさえ感じる人もいるだろう。この同時性は、スターだけが経験する特殊な通過儀礼にも見えるから不思議なことだ。
この洗礼もあったのかもしれないが、映画も芸能ネタ扱いされたり、彼が主人公に適役かどうかを問う原作漫画ファンによる批評にばかり世間の目が行きがちになっていた。しかし『無限の住人』の主役を演じた役者としての木村拓哉、そして作品そのものを映画として捉える必要があるのは確かなはずだ。この視点から映画『無限の住人』を分析する。
木村拓哉なくして『無限の住人』は成り立たない
この映画はスター木村拓哉氏の映画であることは間違いない。だからおのずと関心はスクリーンに映しだされる彼の立ち振る舞い、しゃべり、視線の動き、そして殺陣にいくのは当然だ。変な言い方だが、実際にこの映画はこの繰り返しだ。彼が出ていないシーンは、極限まで短くブツ切りに編集されている。つまり、木村拓哉氏なくしてこの映画は成り立たっていない。
生と死、白と黒、目
死んでおかしくない怪我を負いながら、万次は生き返るように再び立ち上がる。最愛の妹を自分の不覚から殺されながらも、自らは死ねないでいる。死のこの両局面は、白と黒(もしかして濃紺)という相容れない色の着流しによって冷たく映し出されている。
その大ぶりな袖から伸びる両腕、はだける胸元は、切り落とされ刀を突きさされるたびに野蛮さを強く帯びはじめる。その再生に生への執念さえ感じられもする。
ところが手や胸は再生するが、なぜか刀で切られた目はよみがえることはない。血仙蟲(けっせんちゅう)とは、そういうものらしい。それはともかく、死に続ける片方と、生に飢えるようにギラつき剥き出でくるもう一方は、着流しと等しく生き物の両面を同時に宿している。
役に命を吹き込む喜びを知った役者

片目の存在感、それはテレビでよく見るキムタクからは想像できない。テレビドラマでは、もっぱら都会で暮らす格好いい青年の役が多いからだ。それが木村拓哉氏本人だと視聴者は勘違いしている。だがそんなイケメン要素はこの映画には一つもない。
世捨て人同然に生きる万次は、周到に作り込まれた食べ方、物言い、敵に向かう直前に刀を一回転させる仕草、そして目の動きによって存在感ある活力を得る。時に、カメラがピントを合わせてくるのを待っていたかのように、目は焦点を定めもする。映画俳優が台本と演出を超えて、役に命を吹き込む喜び。それを木村拓哉氏がなしえた一瞬と言えよう。
だがこの人ほど不幸な俳優はいないのではないか。視聴率、週刊誌や芸能ネタで真っ先に叩かれ、つねに色眼鏡のかかったゴシップばかりで、演技が話題にされることはほぼない。いつまでもロンバケじゃないでしょと思うのだが、マスコミとはそのようなものなのだろう。おそらく本人は気にしていないのかもしれないが。
登場人物はそこにいたのか
30巻という長い漫画を140分の映画で見せることは到底できない。どこかに焦点を当て、他は削られるという取捨選択がされるわけだ。原作を知っている方にすれば、登場人物や武器などが忠実に再現されているかが出来不出来を決める判断の一つになるのだろう。
しかし全く予備知識がなく鑑賞した立場からすると、登場人物の中には、その存在に首をかしげる者も何人かいたとに感じた。彼らはほんの数分だけあらわれ、二言三言で残酷にあっけなく殺されたり自害する。
原作を忠実に再現したのだろうが取捨選択による物語の凝縮があってもよいわけで、この場合は若干の変更も許される。これが映画化ということで、そんな例はいくらでもある。それによって原作とは違った映画独自の面白さが生まれもする。例えば今作で登場しなくてもよかった代表的な人物をあげるとすると、市川海老蔵氏が演じる閑馬永空(しずま えいくう)と、山崎努氏の伊羽研水(いばね けんすい)だ。
生き続ける虚しさを説けた閑馬永空

閑馬永空は万次と同じように血仙蟲(けっせんちゅう)によってほぼ不死身になり200年生きている人物だ。彼も万次のように愛する人を失い、生きる辛さを背負っている。言わば万次の先達だ。
生と死、殺生のむなしさを万次に教えさとすことができた唯一の人物でありえたはずだ(これだ原作とは真逆の人物設定になってしまうが)。
死は継承と断絶だと予見させられた伊羽研水
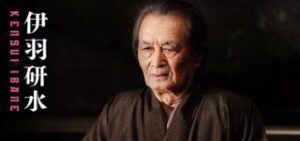
伊羽研水は、自らの流派を逸刀流(いっとうりゅう)二代目の統主である天津影久(あのつ かげひさ)の傘下に組み入れようとするが、その一歩手前で自害する。映画の主流ではないので、その背景は略されている。
伊羽の役目は、流派継承の行く末を鑑賞者に予見させるだけでしかない。その結末は天津によって表されるが、いかんせん伊羽の登場から自害までのシーンが短すぎる。死を継承と断絶の結末として体現できた人物であっただけに、これ以前にもう一場面登場させても良かったのではないか。登場と死姿の間に他の物語がはさまっていれば、伊羽研水の存在を生死の両面でより強く感じられただろう。
閑馬永空も伊羽研水も、死に殺し以外の意味を持たせられる人物になりえた。あと20分物語を長くしてよいなら、主人公との関係を、生きることの虚しさと現実世界の裏切りを描くことができ、映画に厚みを持たせられただろう。
三池らしさで終える人物
また女性の剣士が二人でてくる、どちらか一人でも良かった気もする。一方は金髪で他方はワイヤーアクションという、三池崇史監督でおなじみの要素を体現していただけで終わっている。家を飛び出していった浅野凜(あさの りん)を追いかける万次の前に現れた三人組や、市原隼人氏の尸良(しら)も同じだ。

しかし市原氏が現れたとたん、画面が活き活きとしはじめたのはなぜだろうか。時代劇にサングラスや金髪などの異要素が唐突に出てきたことが、気持ちよくさえある。ここが三池作品を味わう楽しさでもあろう。
カメラ・編集・気迫
アクションで世界に知られた三池監督は、冒頭からその連続で中盤まで引っ張り続ける。そのほとんどは万次の顔のアップか、相手と切り合う上半身のシーンが編集でつながれている。連続するアップ、しかも人が次々に死ぬシーンだ。目が痛くなったり気分も重くなろうが、そんな感じがしない。
おそらく、一つ一つのシーンが素早くないからだろう。細かなショットを連続させてスピード感と迫力を出そうとはしていないのだ。その代りに、殺し合いをしている男を、カメラは比較的近い位置から捉え続ける。カメラは万次の敵でも味方でもなくそこにいる。
カメラ位置を変えるために演技が中段されたとしても、その回数は少なかったのではないだろうか。あらかじめ決めたシーンを一通り撮影し、別の位置にカメラを移動させて続きを撮るといった具合に。
斬られた相手が突然振り返って血を飛び散らせもしないし、切り落とされた首の向こうに万次が刀を構えていることもない。たくみな編集によるショッキングさで観客を驚かそうという意図がないのだ。映画は編集によって演技や演出がより良くも悪くもなる一面を持っているが、この映画は編集で何とかしようと苦心してはいない。
観るのは万次か、木村氏か

長く続く人斬りのシーンを緊張に満たしているもの。それは侍という万次の生きざまであり、役者である木村拓哉氏の気迫だ。この気迫こそが映画『無限の住人』のすべてといえよう。観客がこの男は死なないと知っていることはもはや問題ではない。それは物語の設定でしかない。観るべきもの感じるべきものは、その奥にある。
それほどの役者魂を見せられながら、腑に落ちないのはラストシーンだ。やっと死ねたと思ったが、やっぱり死ななかった。その台詞で物語は幕を閉じる。余韻を残した終わりとも取れるが、オチをつけた形でもある。漫才が「いいかげんにしなさい」と終わるように。
果たしてこの終わり方は映画だけなのだろうか。芝居やアニメでも同じなのだろうか。このような終わり方は、今時の日本映画によく見られる典型例でもある。深読みすれば、ヒットすれば続編をという製作者側の思惑さえ浮かぶ。
生と死という普遍的なテーマを不死によって物語るのは、古典映画『ノスフェラトゥ』やスプラッタームービー『死霊のはらわた』などのでもお馴染だ。これらの作品との比較は主旨ではない。製作された背景が違うので一様に考えないほうがよくもある。
ここまで頭をめぐらせていると、別のラストシーンも考えたくなる。死を殺し以外の面で捉えられる人物が登場していただけに、娯楽アクション映画だとしても別の終わり方があったのではないかと。
例えば決闘の最後の場面。
天津影久は去りゆく。追いかける浅野凜、万次がその後を走る。
天津の剣が浅野を突き刺そうとする間際、万次が身をていして防ぐ。
組み合う天津と万次、浅野。
カーブした刃先が浅野の身体を突き刺した。
またも愛する者を失った万次。
悲しみの咆哮。
翌朝、生きる辛さに絶望しながら歩きはじめる。消えるように。
映画が映画で終わらないために

ハッピーエンドではないが、物語を140分だけで終わらせることなく、観客に考える余地を与えることで映画に参加してもらう終わりかたもあっただろう。読後感の良い本が記憶に残りやすいように、製作者陣は観客の心に向けたエンディングを意識しても良かったかもしれない。現に、同じ時代劇映画で『七人の侍』という傑作もある。
そこに送り手の思想があるかどうか。映画館で過ごす2時間ちょっとが、カラオケやSNSなどとは違う体験を提供できる土台はここにある。思想をエンターテインメントに忍ばせている表現が映画だ。『無限の住人』でもそれは十分にできたはずだ。しかし実際には観て深く入ってこない。なぜなら終わりかたはオチをつけただけだからだ。音楽も大人しい印象だし、本編となんの関係もないエンディング曲はキムタクに負けている。同じく彼が主演した『武士の一分』のように、今作でもその意気込みがそのまま伝わってくるだけに残念だ。
作品は2015年から16年にかけて撮影されて17年春に公開された。このあいだに、つまり2016年年末に木村氏がメンバーだったSMAPが解散したことは世間を大いに騒がせた。
映画のストーリーと実際の彼らを重ね合わせるのは暴挙だと重々承知だが、SMAPの解散という選択は終止符という意味で死とも言い換えられよう。スマスマ最後の放送は、まさに葬式だったという噂もあるほどだ。
でもそれは個々の新たな出発点でもあろう。木村拓哉氏が今作で見せた気迫に、映画を超えて、別の生が始まる5人のスターにエールを送りたくなる。