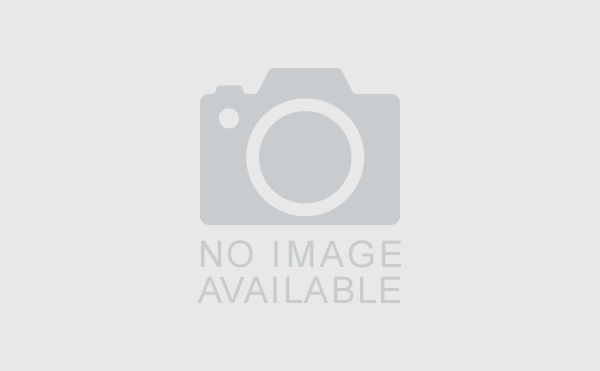これまでに何度見たのかを忘れさせる映画がある。『お熱いのがお好き』はまさにそんな作品だが、単にコメディ映画だから面白いのではない。この作品にはハリウッド流の映画製作の技術、物語の運び方、そして役者がスターとして輝きながら演技をする各要素が結実しているからこそ何度も観返したくなるし、何度見ても飽きないわけだ。
映画好きならすでに鑑賞済みなのは当然だが、たとえこの作品を初めて観る人でも、ハリウッド流コメディ映画の原型かつ集大成がここにあると思い知らされるだろう。一方、製作が1959年というまさにフィルムノワールの時代でありながら、今作の雰囲気は1930年代のままなことに、どんな反応をしてよいのか戸惑いもする。
とは言え公開時も観客にも専門家にも好況だったようで、様々な賞レースを『ベンハー』と争った。ほとんどの部門でトロフィーを逃したものの、衣装だけは受賞していることを考えると、やはり主演マリリン・モンローの存在が大きかったのだろう。
ここでは映画の定番中の定番『お熱いのがお好き』がなぜ何度見直しても面白いのか、その面白さはどのようにつくられているのかを分析する。見て楽しむという観客の立場でいるだけでなく、繰り返しの鑑賞に耐えられる作品を成立させている製作者たちの立場に自分を置くことで、彼らの意図や思いなどをくみ取れるようになる。
ワイルダーが意図した物語の構成

『お熱いのがお好き』の物語は大きく三つに分けることが出来る。これは演劇にも共通する三幕物で、ドイツのヴェルナー・ヘルツォーク(Werner Herzog)監督との対談によると、ビリー・ワイルダー監督も意識していたらしい。そして、物語の結末は観客の実生活にも良い影響を与えるようなハッピーエンドであるべきだと語っている。
今作では女装と恋の絡み合いや、最後の台詞「完璧な人間はいないよ」によって、ハッピーエンドが物語のなかで終わることがなく、観客の心の中に笑いとともに湧き上がってくる。女性解放が盛んになった時代だからだろうか、性に関連づけた点を女性蔑視のジェンダー論にまで発展させる捉え方もあるようだが、この文章ではあくまでも物語の中で、監督をはじめ製作者たちがどのように映画をつくったかに焦点を当てる。
今作の三幕はどれも足元からはじまっている。一幕目はシカゴの駐車場に降りたスパッツの足元だ。物語はこれ以前に隠れ酒場から始まっているが、追われるジョーとジェリーと、追うスパッツ一味の接点はこのシーンだ。
二幕目はジョーとジェリーが女装してジョセフィンとダフネとなり、フロリダへ向かう列車へと歩くシーンだ。カメラはハイヒールでぎこちなく歩く二人の足を後ろから捉えている。この直前に女性を真似た裏声でジョーは芸能事務所に電話をかけるが、そのときの二人の顔のアップから誰とも分からない後ろ足へ、そして女装したジョーとジェリーの上半身ショットへの繋ぎは、観客の気持ちのリズムを落としていないことに気がつくだろう。女性の服に着替えたり化粧の場面はすべて省略されている。いきなり女性として仕上がった二人をスクリーンに映すことで、時間と物語の省略だけでなく、ここに笑いという要素を加えた。それまでサスペンス調だった雰囲気が、一気にコメディに変わった瞬間である。
第三幕目はフロリダだ。オペラ愛好会に参加するためにやってきたスパッツが足元から再登場する。ここでコメディに味を加える形でサスペンス調が復活する。このようにどの幕も足からはじまっているが、足は単に体の器官というだけでなく、様々な意味が含まれて物語を構成する軸になっている。
男の足、女の足

男の足でまずあげられるのが、マフィアのボスであるスパッツの足だ。彼の足元は名前と同じスパッツで厳重に守られている。足元のほうのスパッツの役割は、靴を汚れや小石などから守ることだ。防寒という役割もあるが、お洒落で綺麗好きなマフィアのボスを考えると前者だろう。常夏のフロリダでも足元にスパッツを欠かさないほどだ。糊がきいた白いスパッツは他人と交わらないかのように色がなく、どこか重々しい。足元から横へ広がる形の線は彼を取り巻く四人の男たちへたどり着く。屈強な彼らは高学歴の弁護士で、肉体と知能という両方の力を持ち合わせてスパッツを守る。
今作にはもう一つ男の足が登場するが、その前に女性の足について書いてみたい。まずは性の違いによって足が持つ象徴的な意味を理解するほうが物語の構造を捉えやすいからだ。
女の足であげられるのが、マリリン・モンローのそれであることは疑いようがない。女装したジョーとジェリーが見とれたのは、ヒールを履いたシュガーの足だ。性の対象としてはもちろんだが、ジュリーは履きなれないヒールに足をくじいているのに、難なく歩いてゆく彼女の姿に、機関車が吐きだした蒸気を素早くよけるその身のこなしに驚く。シュガーは二人のことなど知る由もなく列車の乗り口へ向かう。
ジュリーはシュガーという女性そのものに驚いている。自分たち男と違うというだけでなく、男の添え物的な立場だった酒場のダンサーや芸能事務所の事務員とも違う種類の女性、こんな生き物がいると初めて知った驚きだ。ヒールは軽やかな音を立て、脚はスラリと上へ伸びリズミカルに前へ進む。その運びには躍動感があり、目的へ自ら進む意思さえ感じられる。困難などなんてことないとでも全身で示すように。その後姿には自由が感じられる。ここまでの男と女を象徴していた要素とは全く違う要素がシュガーという肉体を持ったのあり、彼女の登場が物語が進む方向を決定づけた。

ストッキングの線が真っすぐかどうか気にするのは見られる美しさと同時に、上昇という人間の意思でもある。歌手という表現者の生き方にも通じるだろう。無学を嘆くことなく、時には嘘をついても自分を良く見せようとする。女性美を際立たせる薄く透き通ったストッキングに包まれ、細いヒールで底上げされたシュガーの足は開放的であると同時に守ってくれるものがない孤立無援の状態だ。しかしそれは自由の代償だと重々承知している。
またそこは秘密の場所でもある。ウィスキーのミニボトルをストッキングに挟んでスカートで隠す。禁酒法時代の酒という人間の欲望をシュガーは女性の表層の陰に持つ。当然のように楽団の女性たちも隠れて酒を飲む。酒は男の楽しみとして描かれているが、実際のところ楽しみには男も女もない。
この男と女の中間が、仰々しい男の世界から逃げ出そうと女装するジョーとジェリーだ。ヒールにてこずったことがきっかけでシュガーという新生物が目に止まる。男として女に恋をし、女として男から逃げる。物語はこの二つの展開によって繰り広げられていく。
男にとっての男の足
男にとっての男の足と少し込み入った話だが、女装した男の物語なのでこの様な分析になる。一つ目は、足は悩ませるものだ。スパッツはウイスキーにスパッツを汚されて気分を害し、女装したダフネはハイヒールに足をくじくが、フロリダでは大富豪のオズグッドがその足に足に見とれる。足は常に男を悩ませる。二つ目は、足は男を動かすきっかけだ。ジョーとジェリーはシュガーを追って列車へ急ぎ、フロリダでは車椅子の宿泊客とホテルマンに変装したがハイヒールを脱ぎ忘れてマフィアの子分たちに見つかってしまう。

このように男にとって足は良い事態をもたらさないが、最後の三つ目だけは違う。足は相手の急所を打つ決定的な武器になっている。浜辺で大富豪ジュニアに変装したジョーが足を出してシュガーを転ばせた。このシーンだけは足が男に強力な手助けをし、シュガーの人生を運命づける。まさにそれを狙ってジョーはわざと足を出したのだが、シュガーは見事にひっかかり大きくジャンプするように転がる。彼女はその策略にまんまとひっかかってしまった。偽物の大富豪に変装したジョーの口八丁にシュガーはやられたというわけだ。
男の顔
男にとっての足が命や人生という根源的な一面に関わっているなら、足から最も遠く離れた顔は男の欲望や理性という一面に繋がっている。その典型的な例が大富豪オズグッドの口を大きく開けた笑い顔だ。ダフネに一目惚れした彼は本能をむき出した笑い顔をするが醜く、さかりのついた猿のようだ。画面に出ただけで芸達者な人だと思わせるジョー・E・ブラウンは顔のつくりそのものが笑いを誘うが動物的な顔を見せるのはオズグッドだけではない。フロリダへ向かう列車で女装したジェリーが見せている。シュガーを射止めたい気持ちをジョーに打ち明けるが、その告白の内容よりも大きく開けた口のほうががより男の本能を表している。

笑顔が男の本能なら、反対の無表情は自分を抑える理性だ。刑事やボスに感情をあらわさないスパッツの顔は計算済みの自己防衛策がなせる技である。もう一人、大富豪ジュニアに変装したジョーがいる。彼も無表情だが、恋人を死なせたトラウマがそうさせていることになっている。こちらも計算づくだ。このように男の笑い顔は性欲をむき出しにした原始的な本能であり、無表情はあえてそうしている理性的なしわざと言える。そしてオズグッドもスパッツも、もう一人ジョセフィンを口説こうとするホテルのポーターも、全員の男が体格が小さい。
男女の名前
中心となる登場人物の関係が男二人と女一人という三人組は恋愛物語の定番だが、今作もそれをなぞっている。それぞれの役柄は名前から探ることができる。ジェリーはジョーにジェラルディンと名付けられたが、自分でダフネに変更した。ダフネはギリシア神話では恋の矢にさされたアポロンから逃れるために月桂樹に姿を変えた女性の名前だ。今作のダフネは大富豪オズグッドから逃げている。また思春期の世代や処女が抱きがちな同性への恋心と純潔、男性恐怖症を意味するダフネコンプレックスとしても用いられる。ジョセフィーヌはジョーの変形で、歴史から探せばナポレオンの妻が思い当たるが今作に相応しいかは疑わしい。
シュガーは甘いケーキそのものだ。彼女の体は男にとっては甘い獲物だが、実際の彼女は子供の頃の姉とのお遊びや恋にいまも憧れている。純朴だが妄想とも言える。

ジョーもジェリーもこの甘さにやられてしまう。スパッツまでもだ。彼は砂糖の塊であるケーキの偽物に隠れていた殺し屋に銃で撃たれてしまった。その殺し屋ジョニーはスパッツを演じたジョージ・ラフトと何度も共演したエドワード・G・ロビンソンの息子だ。父親の名前にジュニアとつけた男優はハリウッドでそれほど目立った活躍をすることなく若くして亡くなった。その名前が先祖名を受け継いだ偽の大富豪と同じなのは偶然の一致かもしれないが。
チャールズ・ラングのカメラ、オリー・ケリーの衣装
『お熱いのがお好き』は脚本の段階で物語の構造が完成しているが、もう一つの側面を忘れることはできない。主役のマリリン・モンローを見る楽しみだ。極言すれば、スタッフはあらゆる技術をもちいてマリリン・モンローをいかに魅力的に見せるかに取り組んだのであり、観客はその出来栄えに酔いしれる映画なのだ。カメラマンのチャールズ・ラングは常に中央にいるモンローを背景から浮き立たせるように撮影し、彼女に女神のような崇高さを与えている。シュガーがステージで歌うときは暗闇に輝く強烈な光を彼女に与え、それ以外のシーンではモンローの顔に影を落とすことなく自然に見えるように、たとえ夜であろうと背景を明るくさせている。

オリー・ケリーの衣装はモンローの体の曲線の上を流れているようだ。シカゴでの重くて黒いコートからフロリダでの日中の薄い白いワンピースへの移り変わりは気持ちの解放感も表している。ステージで光り輝く黒いドレスは、小さなフリルやスパンコールがシュガーの夢物語を演出しながら、一方ではモンローの体の線を暗闇の中に浮きだたせて裸以上に欲情的だ。唯一アカデミー賞を獲得した衣装部門だが、モンローを魅力的に見せているからかもしれない。モンローは現代でもセックスシンボルと見られているが、今作の歌うシーンと『七年目の浮気』でのスカートがめくれ上がるシーンがそれを成しえている。後者は健康的だが、前者は体に肉づきがよいことで性的な一面がより出ている。
シュガーを表出する背景セット
撮影や衣装はマリリン・モンローを魅力的に演出している、シュガー・ケーンの気持ちや性格を肩代わりして描写した背景セットを見落とすことはできない。それらは様々なシーンでモンローが動く背後に見られる。
フロリダへ向かう列車のトイレで、シュガーはこれまでに幾つものバンドを渡り歩いたと打ち明けるが、その後ろの車窓の外を光が素早く横に流れている。おそらく電柱の電灯だろうが光の瞬きのようであり、流れ星のようであり、シュガーの数々の失恋も連想させる。
後のシーンで、ジュニアが待つ波止場へ走るシュガーは、新たな恋のはじまりに胸をときめかせている。ショーが終わって外は暗いはずだが、バストショットで捉えられた彼女の後ろに夜の暗さはない。この直前にダフネとオズグッド3世の横をジョーが自転車に乗って通り過ぎるが、周囲は真っ暗だ。それなのに次のシュガーのショットでは背景から暗さが消されて、どこか人工的な薄ぼんやりとした明るさがある。暗闇のなかでモンローの顔に影を落とさずに撮影するとなると不自然さが出てしまうだろう。またこのシーンのシュガーは恋に憧れる少女ということもあり、その気持ちに合った画面の色調を優先したのかもしれない。

桟橋へと走るシュガーの気持ちを背景セットが最も鮮やかに演出するシーンがこのあとに続く。シュガーは砂浜沿いに並ぶビルの前まで来た。1階は洋服店なのか天井が高いガラス張りのショーウィンドーだ。その前をモンローは横切るが、マネキンも洋服も飾られていない真っ暗なショーウィンドーの天井に幾つもの照明が消し忘れられている。その前をモンローが横切るが、瞬間的に体が照明をさえぎって光の帯を点滅させている。かつての列車では、自分とは関係なく光は背後を流れていくだけだったが、ここでは自ら動いて光に生命を与えている。その瞬きはシュガーの鼓動にも見える。
砂浜を駆け抜けて桟橋へたどり着いたシュガーを波間からカメラは捉えるが、背景が全体的に明るくてスタジオのセットのように見える。だが背景の右奥を人影らしいものが動いていることから、そうとも言い切れない。スタジオセット内の遠く後ろを人が歩くことはないだろうから、ロケーション撮影中に偶然に映り込んだのかもしれない。何はともあれ、真夜中にもかかわらずこの明るい背景はマリリン・モンローの全身をはっきり見せるためだろう。

だが次のシーンでは画面に夜の印象がある。ボートに乗ったシュガーがまとう毛皮のマフラーには、柱の隙間から漏れる月の光の影が落ちている。実際に桟橋で撮影中の写真があるが空は暗くない。もしかすると昼を夜にする「アメリカの夜」で撮影されたのかもしれない。
ステージを終えたシュガーがボートに乗るまではほんの数十秒のシーンだが、モンローの演技とスタッフの技術によって、歌うシーンに並んで彼女の魅力をスクリーンに写している。
第四の主人公たる音楽
映画音楽は第三の主人公と言われることがある。物語の展開を予感させたり、人物の心理をうかがわせたり、シーンを盛り上げたりなど、役割は多岐にわたる。『お熱いのがお好き』には主人公が三人いるから音楽は第四番目となるが、1930年代後半から60年代にかけて年に何本も担当していた作曲家アドルフ・ドイッチェによる今作の音楽は、自分も主人公だと宣言するように冒頭から存在を示している。
かつて1930年代から制作されていたスクリューボール・コメディの映画音楽では、作品を印象づけるリズムとともに冒頭のクレジットがはじまり、軽快な曲調でエンディングを締めくくって観客に好印象を残していた。良く知られている映画としてはエルンスト・ルビッチ監督『極楽特急』(1932年)、ハワード・ホークス監督『赤ちゃん教育』(1939年)、フランク・キャプラ監督『ある夜の出来事』(1934年)などが挙げられるだろう。
だが1959年というスクリューボール・コメディとしては時代が経ってしまっている『お熱いのがお好き』の音楽は、映画を盛り上げる脇役に納まっているだけではない。三人の主役とならんで自分がいると高らかに主張している。
オープニングでマリリン・モンロー、トニー・カーティス、ジャック・レモンの名前がトランペットの三つの音とともに現れ、四つ目に映画のタイトルが現れる。「Runnin' Wild」の軽快なリズムが流れてクレジットが終わるが、その最後に三人を象徴する三つの鐘の音が鳴る。こうしてオープニングの音楽はアップテンポから一気に低音へ下がるが、まるで音楽自体が一息ついているようで、この急激な変化が観客の気持ちの準備を整えるように物語へ誘っている。音楽はつねに流れて物語の雰囲気を強めているが、人物よりもゼロコンマ秒だけ先に登場して音によって心理を描写するなどはハリウッド流の映画音楽だ。
冒頭のクレジットで作品の特徴を示し鐘の音で人物を登場させた音楽は、エンディングの最後では自らの存在を示している。大富豪の「完璧な人間などいない(nobody's perfect)」で終わる物語にオチをつけるようなトランペットのスタッカートのリズムではじまり、再び「Runnin' Wild」が流れる。そして鐘が三回鳴りオーケストラの大合奏で終わる。三つの鐘の音は主役三人と捉えることもできるが、物語の結末と併せると教会の鐘が連想できる。教会は愛を誓う場所、結婚は男女の恋愛のゴールインだ。愛、結婚、ゴールインを知らせる鐘が鳴り、祝福するようにオーケストラの大合奏が鳴り響く。鐘に続く大合奏は物語のハッピーエンドを一層盛り上げている。
また、エンディングにはクレジットロールがなく真っ暗な画面に音楽だけが流れていることも忘れてはいけない。これによってハッピーエンドの心地よい余韻が観客に自分事のように感じさせることに成功し、それを成しえたのが音楽なのだと自ら主張しているようだ。観客に気持ち良く映画を見終えてもらおうという意図は、ビリー・ワイルダー監督の考えとも合っている。
このように人物に先走って心理を描写したり、主役を凌駕するほどの存在感を示している音楽だが、一か所だけその座を登場人物に譲っている。マフィアから逃げようと大富豪のボートに乗ったジョーとダフネを追いかけて、シュガーが桟橋の階段を上るシーンだ。息を切らせるシュガーの気持ちは、偽の大富豪と待ち合わせた一度目の時とは全く違う。お金も優雅な生活も関係なく、本当に求めていた恋をつかむために駆け上がる彼女の両脚の動きは、音楽の小刻みなリズム以上に素早い。編集でフィルムの回転速度をあげたために足の動きが早くなっているようにも見える。恋焦がれている女性心を体現しているマリリン・モンローを、スタッフが一度目とは違う技術をつかって表現したのかもしれない。感情と動作が映画的に結びついて、この作品の中で最も激しいシーンを成り立たせている。桟橋の二つのシーンは、マリリンモンローの魅力の一つである可愛らしさに溢れている。
モンローが決定づけた三曲の印象

モンローは列車で「Runnin' Wild」、フロリダのステージでは「I Wanna Be Loved by You」と「I'm Thru With Love」と3曲歌っている。どれも彼女の溌溂さや艶めかしさに満ちていて、まるでこの作品で歌うために作られたオリジナル曲のようだが実はそうではない。「Runnin' Wild」は1922年、「I Wanna Be Loved by You」は1928年、「I'm Thru With Love」は1931年に発表されていて、どれも当時は良く知られた曲だったようだ。「Runnin' Wild」はジャンゴ・ラインハルト(Django Reinhardt)やグレンミラー(Glenn Miller)、ベニーグッドマン(Benny Goodman)なども演奏し、「I Wanna Be Loved by You」はアニメのベティ・ブープ(Betty Boop)の創作元になり、「I'm Thru With Love」はジャズスタンダードナンバーとしてビング・クロスビー(Bing Crosby)やサラ・ヴォーン(Sarah Vaughan)などが歌っている。
しかしこの3曲を後世まで残る名曲としたのはマリリン・モンローだろう。どの曲も彼女が映画で歌うまでは抑揚に乏しく、どこか牧歌的な曲調で歌われている。それがモンローが歌いだしたとたん、曲に血が通ったように激しく鼓動し、艶をおび、悲しみに沈む。映像の力もあるだろうが、編曲者に加えてモンローの曲の解釈と表現は他に代えがたく素晴らしい。受け継がれていた曲のイメージを彼女が一新し、それが決定的なものに、唯一のものになった。
モンローとコメディの最後

三人が主役の作品だが中心にスターとしてのマリリン・モンローがいるのは間違いない。その証左としてもう一つ付け加えるなら、芸能事務所の事務員やオーケストラバンドのメンバーといった他の女性があげられる。事務員やバンドマスターは目鼻立ちは整っているが顔の厚い肉と紋切型の物言いもあり、わざと醜い役柄を演じている。一方のバンドメンバーたちは頬に肉がなく三角形の尖った顎で細い体が貧弱に見える。彼女たちに囲まれたモンローは、そのふくよかな上半身と丸顔が周りを引き寄せる力を持ち、すべての中心になっている。二の腕や腰まわりの肉付きは色気で魅了するにはギリギリの境界線かもしれない。妊娠初期だったという噂もある。33歳という年齢を考えても、ヒロインとしては最後の年齢だろう。実際に3年後に死を迎えてしまうが、この間に出演した2作で今作ほどの魅力を出せたかは疑わしい。『お熱いのがお好き』はモンローが自分が持っている色気を映像として残すことに成功した最後の作品と言ってよいかもしれない。
最後という言葉はモンローだけでなくスクリューボール・コメディにも当てはまる。1930年に大量生産されたこのジャンルをなぞるような物語の構造と人物の関係、撮影や照明などの制作スタッフの細やかな仕事ぶり、人格をそなえた音楽、そして見た目の良い俳優など、どれもが時代を遡って作られたかのようだ。女装したトニー・カーチスとジャック・レモンを醜く見せないために白黒映画にしたというが、それよりもワイルダー監督の30年前への郷愁が本当の理由ではないかと思えてくる。周囲にはフィルム・ノワールや社会性を持った作品が目立ちはじめ、ニューシネマの芽生えも近い。そんななかビリー・ワイルダー監督は『お熱いのがお好き』を最後のスクリューボール・コメディをつくろうと意識していたのだろうか。
今作は日本ではモンローの映画で、なぜか大人が見る作品だと思われている。映画館で上映されることもまずない。しかし世界では歴史に残る名作として広い世代に見られている。フランスでは子供にこそ見せたい映画と言われている。実際フランスを旅行中にダンケルクの映画館で小学校の課外授業なのか先生に引率された大勢の子供たちと一緒に鑑賞したが、みんな大笑いしていた。ああ、これが文化の差なんだろうなとつくづく思った。
『お熱いのがお好き』は遅れて来たスクリューボール・コメディであるだけに、その集大成とも言えるかもしれない。
物語、技術、スターという三つの要素が結実しているからこそ、繰り返しの鑑賞でも新たな楽しみが見出せる。そこから過去の作品にも関心が広がるだろう。
世界には観ていて当たり前という映画が存在する。もし自分は映画好きというなら何度も観ていて当然だ。一度も見たことがないでは済まされない。それが『お熱いのがお好き』という映画だ。