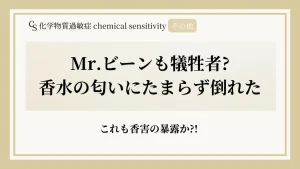化学物質過敏症の鍵はマスト細胞:免疫学博士テオハリス・テオハリデス氏の対談動画
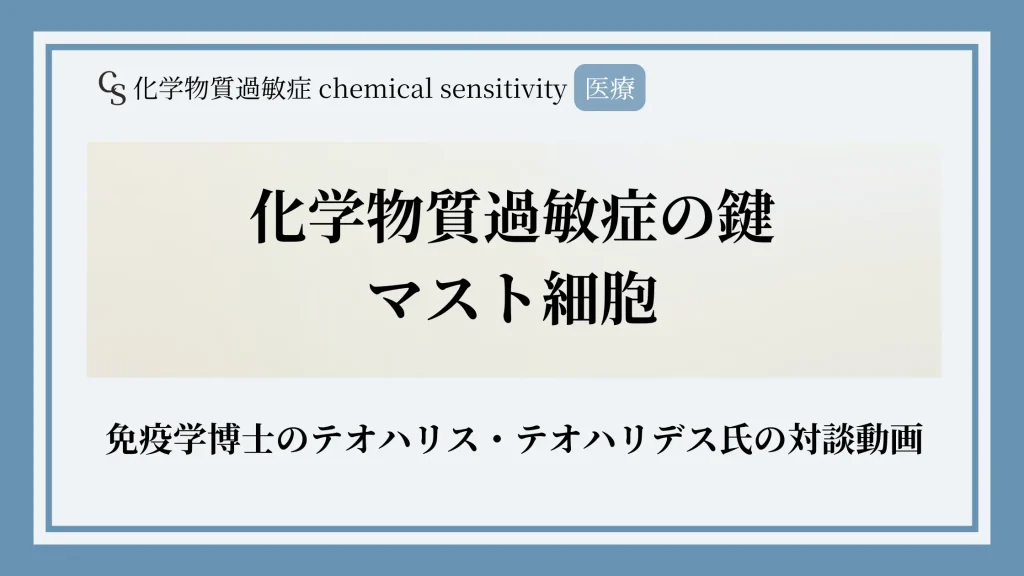
化学物質過敏症が単なる「心身症」や「気のせい」ではなく、客観的な科学的根拠によって説明できると話す専門家がいます。テオハリス・テオハリデス博士 (Dr. Theoharis Theoharides)です。
博士は、MCSの症状とは微量の化学物質によって体内のマスト細胞(肥満細胞)が過剰に興奮・活性化される「マスト細胞活性化症候群(MCAS)」であると特定しました。
これにより、MCSは脳と全身の細胞レベルで起こる明確な物理的・免疫学的疾患として定義づけられ、診断と治療の新たな道筋が開かれています。
テオハリス・テオハリデス博士とは?
動画の概要では、テオハリス・テオハリデス博士を次のように紹介しています。もちろん英語なので、翻訳ソフト「DeepL」で日本語に翻訳しました。
博士は神経免疫医学研究所-クリアウォーターの教授、臨床免疫学副部長、所長を務め、タフツ医科大学では免疫学の客員教授(同大学では薬理学・内科学教授、分子免疫薬理学・創薬部門長、マサチューセッツ州医薬品処方委員会臨床薬理学者も歴任)である (1983-2022年)。
イェール大学にて学士号、修士号、哲学修士号、博士号、医学博士号を取得し、病理学分野でウィンターニッツ賞を受賞。
タフツ大学フレッチャー法律外交大学院にてグローバルリーダーシップ修了証書を取得、ハーバード大学ケネディ行政大学院にてフェローシップを修了。
ニューイングランド医療センターにて内科研修を行い、「卓越性、思いやり、奉仕を称える」オリバー・スミス賞を受賞。テオハリデス博士は485本の論文を発表(被引用数46,491回、h-index 106)し、世界で最も引用される著者の上位2%に位置付けられ、Expertscapeによりマスト細胞の世界的専門家と評価された。
アルファ・オメガ・アルファ医学栄誉協会、希少疾患殿堂、世界科学アカデミーの会員に選出されている。
と、想像も及ばない経歴の持ち主です。しかし動画では専門的な医学用語も極力使われず、その穏やかな語り口が人柄を感じさせます。
まだ新しい学説なので何とも言えませんが、MCSという病態の根本を理解するための貴重な情報源となるかもしれません。
YouTube動画「ヘイリー・ポムロイ氏とテオハリス・テオハリデス博士の対談」
こちらが動画の本編です。
Institute for Neuro-Immune Medicine(略称INIM)という、米国フロリダ州のノヴァ・サウスイースタン大学(Nova Southeastern University)に設置されている神経免疫疾患の研究・医療機関のYouTubeチャンネルに、2025年7月8日にアップロードされました。
博士と対談しているのは、アメリカで著書『The Fast Metabolism Diet』がベストセラーになった作家で栄養士のヘイリー・ポムロイ(Haylie Pomroy)氏です。
日本語の字幕を表示させたり、日本語の音声に切り替えられます。動画をスタートさせて、画面右下の歯車をクリックして、字幕や音声を日本語に設定できます。
動画の文字起こしを要約
聞いただけでは理解できないので、まずは動画を文字起こしして、それをGoogleのNotebookLMでまとめました。
NotebookLMの要約はまとまっていました。でも気持ちを汲み取れていないようで、博士の思いが伝わってこない感じです。
なので、文字起こしをした英語文をgeminiとChatGPTでそれぞれ日本語に訳して、要約させました(AIは文字からその人の思いや心理も読み取った文章を作成するので)。
要約文を互いに読み込ませて、補足したものが次の要約です。この要約を読むと、テオハリデス博士が抱いている無理解な世間への憤りも感じられてきます。
MCSの定義と社会的誤解
- 多種化学物質過敏症(MCS)は、ベンゼン、アルコール、食品添加物、ホルムアルデヒドなど、環境中のごく微量の物質に反応して発症する複雑な症状群
- 「特発性環境疾患(Idiopathic Environmental Illness)」など複数の名称で呼ばれるが、統一された定義はなく、診断は極めて困難
- 微量で発症する特性から、依然として多くの専門家が「心因性」「想像上の病気」と片付け、誤診や社会的無理解が横行している
- 博士は「心身症コードを当てはめるのはナンセンス」と批判し、診断には「Mast Cell Activation, Unspecified(マスト細胞活性化症候群・特定不能)」を使うべきだと主張
- MCSを持つ人は「炭鉱のカナリア」のように、環境の危険を先に感知している可能性がある
MCSとマスト細胞活性化(MCAS)
- MCSに関連するトリガーは、すべてマスト細胞を刺激する
- マスト細胞は骨髄由来で、血管や神経の末端、皮膚、腸、膀胱、そして脳にまで存在
- 従来「IgEを介するアレルギー細胞」とされてきたが、実際には化学物質、真菌、細菌、ウイルス、温度、ストレス、振動など約300種類の受容体を介して反応する多機能細胞
- 一度活性化すると、即時反応して顆粒内の分子(約1000種類)を放出
- 遅延反応:約6時間後にさらに分子を合成・放出
- これにより影響は全身に及ぶ
- アレルギーは氷山の一角にすぎない
- 博士は「研究がヒスタミンやロイコトリエンに偏り、放出される数百の分子を無視している」と強調
ストレスと脳の関与
- 匂いの情報は嗅神経を通じて視床下部へ
- 視床下部はストレスホルモンCRH(コルチコトロピン放出ホルモン)を分泌し、マスト細胞を刺激
- CRHは「敷居を下げる」作用を持ち、通常100単位必要だった刺激が10単位で反応を起こすようになる
- このため、MCS患者は微量曝露でも強い症状を示す
- CRHは脳だけでなく皮膚・腸・膀胱でも分泌され、全身の過敏状態を悪化させる
- 博士は「匂いは進化的に危険を察知するセンサーだった。だから現代の化学物質も警報信号として作用する」と指摘
診断と検査
- 米国にはMCS専用の診断コードがなく、心身症コードで処理されることが多い
- 簡易チェック:皮膚スクラッチテスト(ひっかき後2分以内に赤くなるか)
- IgEを介さないため、RASTなどの血液検査は陰性になることが多い
有用な生物学的の指標
症状の重症度と強く関連する指標として、以下の分子の測定を推奨しています。
- 炎症性サイトカイン: インターロイキン6(IL-6)、血管内皮増殖因子(VEGF)
- 免疫関連: 総IgE、食物不耐性に関連するIgG1とIgG4
- 抗酸化能: グルタチオン、ビタミンD3
- 環境毒素の検査(補足)
- 重金属検査の解釈: 重金属は毛髪に永続的に留まるため、血液検査が陰性であっても、曝露がないことの証明にはならない
- マイコトキシン(カビ毒):曝露源はカビの生えた建物だけでなく、約50%が食品から来る。カビ毒は尿中などで測定されるが、検査の解釈には注意が必要
治療と対策
- 第一歩はトリガーの回避
- 活性炭入りマスクは匂い遮断に有効
- 一般的な3Mマスクはウイルスには有効だが匂いは防げない
- 消臭スプレーや香料製品に対して、消費者の声を届けることが重要
- マスト細胞のブロックが根本的アプローチ
- 天然フラボノイド「ルテオリン」(オリーブオイル配合で吸収性向上)
- ビタミンD3:抗アレルギー作用。博士は1日5,000IU1程度を推奨
- 腸の健康回復が最重要。腸内バランスが整うと全身炎症が減り、免疫療法も効果を発揮しやすくなる
- 抗酸化サポート(グルタチオンなど)も役立つ
- 5,000 unitsは、IU(International Units/国際単位)を指します。
ビタミンDでは、1 IU = 0.025 µgに換算されます。
(マイクログラム:microgram=1mgの千分の1、1gの百万分の1)
5,000 IU = 125 µg(マイクログラム) のビタミンD3に相当します。
日本のサプリメントは IU ではなく µg 表記が多いので、換算すると分かりやすいです。
・1,000 IU = 25 µg
・2,000 IU = 50 µg
・5,000 IU = 125 µg
博士が5,000 IU/日を推奨する理由は、世界的に約40%の人がビタミンD不足とされ、日光に当たっていても血中濃度が足りない場合が多いからということです。ビタミンD3には、マスト細胞の反応を抑え、炎症や過敏性を和らげる働きが期待されます。
ただし、日本の厚生労働省が定める耐容上限量は 100 µg(=4,000 IU)/日なので、博士の推奨する 125 µg(=5,000 IU)/日 は、それをやや超える「高用量」になります。 ↩︎
まとめ
- MCSは「心因性」ではなく、マスト細胞の過剰活性化を基盤とする疾患である
- 匂いを介した脳—免疫系のクロストーク、ストレスホルモンCRHによる閾値低下が、微量曝露でも重い症状を引き起こす
- 社会的誤解と研究の遅れが患者を苦しめており、博士は「診断コードの是正」と「マスト細胞を標的とする治療」を強く訴えている
補足と個人的な感想
AIの要約には出てこなかったことで注目した点として、Shite hospital in Berlinでは、病院やホテルやスパなどを検査して、化学物質過敏症に関わるものが一切ないかを確認してくれる組織があるそうです。この施設は、シャリテー – ベルリン医科大学と思われます。
ですがこの医科大学のウェブサイトに、組織に関する記述は見当たりませんでした。
対談者のヘイリー・ポムロイ氏は普段から乾燥ビタミンCを3g摂取し、何らかの化学物質に曝露したときは、ビタミンCと一緒にビタミンD3、ビタミンK2を摂っていると言います。すると「敏感でなくなる」そうです。「そしてより強く、より心強く、より反応しにくくなったように感じる」と。(it makes me less sensitive. So I feel stronger and heartier and less reactive.)
また、博士はマスト細胞を防ぐためにルテオリン(lutoli)を用いた「ピュアルート(PureLut)」というサプリメントを開発しました。でも日本では購入できません。iHerbでも取り扱いしていません。
アメリカのアマゾンのほか、テオハリデス博士が設立した栄養補助食品の会社Algonotのウェブサイトで販売しています。海外発送にも対応しています。
PureLut: Natural Supplement for Brain Health(Algonot)
SNSのXで検索すると、倦怠感やブレインフォグ対策としてAlgonotから直接買った方もいます(化学物質過敏症ではないようですが)。
感想
動画を全て理解している訳ではないですが、発症の原因となった物質や出ている症状などは当てはまっています。また述べられている必要な対策も、納得できる内容です。
博士は「敏感」という言葉は、「我慢すれば乗り越えられる」と誤解させることがあると言います。だからこそ、体で何が起きているのかを明確にすることが必要だと。
単なる疲労やブレインフォグ、認知機能の問題として片づけられてしまうこともある。でも「耐えられない」のではなく、実際に免疫反応が起きていて、本当に深刻なんだと語気を強めて話しています。
一方では化学物質過敏症の患者も、ホテルのように香りをサービスとして提供している施設などに意見を述べていくことが大切だと言います。
化学物質過敏症の者は、敏感という単語に「自分は弱い」とか「悪いのは自分」といった思いを勝手に抱いてしまいがちになります。でも博士はそれは違うと言います。単に免疫の反応が起きているだけだと。
世間は冷たく、理解しようとはしない。だから声を上げていくことが大切だと。このような見解はとても参考になります。実践していきたいですね。